2025年4月より放送開始となった注目のアニメ『TO BE HERO X』は、日中のトップ企業であるbilibiliとアニプレックスがタッグを組んで制作された完全オリジナル作品です。
“信頼が力になる”という斬新な設定と、映像・音楽・演出すべてにおいてハイクオリティなこの作品が、なぜ日中合作で誕生したのか?
本記事では、制作の背景や意図、監督Haolin氏のビジョン、そしてbilibili×アニプレックスという国境を越えた連携の意義について、徹底的に深掘りします。
- 『TO BE HERO X』が日中合作で制作された背景
- 監督Haolinの演出哲学と“新しいヒーロー像”の狙い
- グローバル展開を見据えた配信戦略と今後の可能性
『TO BE HERO X』はなぜ“日中合作”として生まれたのか?
bilibiliとアニプレックスの協業がもたらすシナジー
『TO BE HERO X』は、中国の動画配信大手bilibiliと、日本のアニメ制作の中核を担うアニプレックスによる共同制作で誕生した完全オリジナル作品です。
このタッグは、単なる出資協力ではなく、bilibiliが持つグローバルなマーケティング戦略と、アニプレックスの高度な映像・音楽制作ノウハウを掛け合わせた、極めて戦略的な連携となっています。
国境を越えて築かれたこの協業体制こそが、本作のハイクオリティかつユニバーサルな作品性を支えているのです。
中国での先行人気と世界配信を前提とした戦略
『TO BE HERO X』は、中国での先行プロジェクト『TO BE HERO』シリーズの続編的立ち位置として開発され、初期段階からbilibiliユーザーを中心に高い関心を集めていました。
この背景から、制作時点で「全世界同時配信」を視野に入れた構成がなされ、NetflixやCrunchyrollなど主要プラットフォームでの展開が実現しています。
グローバル市場を前提とした設計により、あらゆる視聴者が“入りやすく、惹き込まれる”アニメとして完成度が高められているのです。
「信頼」を軸にしたテーマがグローバルに刺さる理由
『TO BE HERO X』の核となるテーマは「信頼」。
“人に信じられることで力を得る”という設定は、現代社会におけるSNS評価や承認欲求ともリンクし、世界中の若者が共感しやすい要素となっています。
また、国や文化を問わず通じるテーマ性により、「正義」「ヒーロー像」への多様な解釈を許容しつつ普遍的な感動を提供する、グローバルアニメとしての強さを持っています。
監督Haolin(リ・ハオリン)が語る“世界で戦うアニメ”の哲学
『時光代理人』『詩季織々』など話題作を手掛けた異才
『TO BE HERO X』の総監督を務めるのは、中国出身でありながら日本のアニメ文脈を深く理解するクリエイター、Haolin(リ・ハオリン)氏です。
彼はこれまでにも、『時光代理人 -LINK CLICK-』や新海誠作品の系譜を感じさせる短編映画『詩季織々』などを手がけ、その高い演出力で注目を集めてきました。
感情の“余白”を描く巧みな演出と、映像美へのこだわりは、今作でも遺憾なく発揮されています。
スタイル横断型アニメーションの新たな挑戦
Haolin監督が『TO BE HERO X』で挑んだのは、ジャンルやスタイルに縛られない“横断型アニメ表現”の構築です。
2Dと3DCGを融合させた映像表現、シネスコ比の演出、アイドル的キャラソングまで、多様なメディア文法を1本の作品に詰め込んだ野心作として評価されています。
これは単に多様な視覚効果を狙っただけでなく、“アニメーションでしかできない体験”を突き詰めた結果でもあります。
「Xは新しいヒーロー像」──その真意とは
監督はインタビューで、「Xというキャラクターには“固定された正義感”をあえて持たせていない」と語っています。
その理由は、現代における“ヒーロー像”が多様化し、絶対的正義が通用しない時代になったから。
Xはあくまで「人に信頼されたい」と願う1人の存在であり、その姿こそが今の社会における“新しいヒーロー像”を体現しているというわけです。
Haolin監督の思想が詰まったこのキャラクターは、今後のアニメの価値観にも大きな影響を与えるかもしれません。
アニプレックスが本気を出す“日曜朝アニメ”新枠の本質
『ワンピース』後の新枠に挑むアニプレックスの戦略
『TO BE HERO X』は、長年日曜朝を支えてきた『ワンピース』の放送枠後継作品という位置づけで、アニプレックスが新たに挑戦する大型プロジェクトです。
この枠は伝統的に“ファミリー層”向けが多く、その中でSF・ダーク・スタイリッシュといった要素を含む本作は、明らかに“新しい風”として打ち出された試みとなっています。
アニプレックスがこの時間帯に全力投球する理由には、視聴の習慣化・話題性・配信との連動といった現代のアニメ市場の変化が背景にあります。
フジテレビとのタッグが実現する放送×配信の最適化
『TO BE HERO X』は地上波放送と配信を同時に意識した制作体制を採っており、フジテレビとアニプレックスのメディア戦略が緻密に連携しています。
このタッグにより、「放送の信頼性」×「配信の柔軟性」という理想的な視聴環境が整備され、幅広い層へのリーチが可能になっています。
さらに、番組放送後すぐにNetflixやbilibiliで配信されることで、国内外のファンがほぼ同時に話題を共有できる構造が構築されているのです。
“子どもも大人も夢中になれる”コンテンツ設計
一見スタイリッシュで難解そうに見える『TO BE HERO X』ですが、その裏にはしっかりとした全年齢層に向けたコンテンツ設計がなされています。
たとえば、ヒーローの活躍や友情といった王道要素は子どもに、人間ドラマや社会風刺は大人に刺さる構成です。
アニプレックスはこの“二重構造”によって、感性の異なる世代すべてを巻き込む作品を目指しており、それこそが本作の広がりと奥深さの鍵となっています。
ビリビリが描く“世界アニメ市場”への野心
中国発×日本制作=“第3のアニメ”の可能性
中国の動画プラットフォーム大手bilibili(ビリビリ)は、近年アニメ事業において急成長を遂げており、“中国発×日本制作”という新たな形のアニメ制作を積極的に展開しています。
『TO BE HERO X』はその象徴ともいえる作品で、従来の「日本式」や「中国式」ではない、“第3のアニメ文化”を創出する試みとして注目されています。
文化的なハイブリッド性とグローバル目線でのストーリーテリングは、今後の世界アニメ市場におけるゲームチェンジャーとなる可能性を秘めています。
『TO BE HERO』から続くIP戦略とファン形成
本作は、bilibiliが2016年に手がけたオリジナルアニメ『TO BE HERO』から続くシリーズ作品です。
このIPは、中国国内のファンベースを起点に、継続的なブランディングと展開を重ねてきた長期プロジェクトであり、続編である『TO BE HEROINE』を経て、ついに『X』へと到達。
シリーズごとにアートスタイルもテーマも変えながら、「信頼」「成長」「矛盾」など普遍的なテーマを軸にファンの支持を得てきたのです。
全世界同時配信の仕組みとその効果
『TO BE HERO X』は、世界約100以上の国・地域で同時配信という画期的なリリース体制を採用しています。
これにより、SNSを通じた“リアルタイムの世界的反応”が加速度的に拡散し、放送のたびにTwitterやWeiboのトレンドにランクインするなど、グローバルでの話題性を確立。
このように、“国内で流行ったら輸出”ではなく、“最初から世界を狙う”アニメ制作の新しい形を体現しているのが、本作最大の特長です。
TO BE HERO X 制作背景・中国×日本合作の挑戦まとめ
国境を越えた協業が生むアニメの新しい未来
『TO BE HERO X』は、中国のbilibiliと日本のアニプレックスという、2つの強力なアニメプロデューサーが手を組んだ国際共同プロジェクトです。
この日中協業によって生まれた作品は、制作体制・表現方法・配信戦略のすべてにおいて、従来のアニメの枠を超える試みとなりました。
今後、国境や言語を超えたアニメ制作のスタンダードモデルとして、さらに多くの作品がこの流れを踏襲することが予想されます。
“信頼”というテーマが示すユニバーサルな力
『TO BE HERO X』が全世界で共感を集める最大の要因は、その核にあるテーマが「信頼」という普遍的な価値観であることです。
国籍や文化を問わず、誰かを信じ、誰かに信じられることで強くなるという構造は、視聴者一人ひとりの心に届くメッセージとして機能しています。
このテーマが、多様化する現代のヒーロー像を形づくる新たな基準として、アニメ業界に大きな影響を与えることになるかもしれません。
今後の展開・続編・メディアミックスにも注目!
すでに『TO BE HERO X』の人気を受けて、関連グッズ、音楽ライブ、海外イベント展開などのメディアミックスが始動しています。
また、続編の構想やスピンオフ企画の存在も関係者インタビューで示唆されており、今後の展開からも目が離せません。
“信頼”と“表現の革新”を武器に、アニメの未来を切り拓く『TO BE HERO X』。その挑戦はまだ始まったばかりです。
- 日中共同制作によるグローバル志向のアニメ戦略
- 監督Haolinが描く“新しいヒーロー像”と演出哲学
- 「信頼」が力になるという普遍的テーマの魅力
- 2D×3D表現や楽曲で高まる映像・音の融合性
- bilibili×アニプレックスが創出する“第3のアニメ文化”
- 全世界同時配信による話題性とSNSでの拡散力


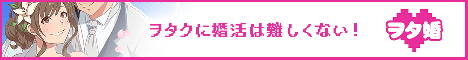


コメント